こんにちは。「minimalish life」をご覧頂き、ありがとうと座います。アフリカ大陸のほぼ真ん中に位置する、ルワンダより通常はお届けしています。この記事を書いている2022年夏は、日本に一時帰国中です!
今回の一時帰国のメインイベントは第二子の出産です。初めての時と同じく、荻窪にある「東京衛生アドベンチスト病院」で出産をしたくて、はるばるルワンダから戻ってきました。
東京アドベンチスト衛生病院(通称「衛生病院」)は無痛分娩に強いといわれている病院だからこそ、二人目もここで産みたい!と思っています。
この記事では、私が無痛分娩を選んだ理由&友達におすすめをしている理由についてご紹介します。少しでも無痛分娩に興味のある妊婦さんの背中を押せたらと思います。
・無痛分娩が気になっている方
・出産方法について調べ中の方
・初めての妊娠で不安な方
妊娠経験2回とも無痛分娩で出産を望む理由

2019年に第一子を妊娠した時に、無痛分娩という出産方法があると知り、「そんな選択肢があるなら間違いなく無痛分娩が良い!」と直感で判断しました。
日本ではまだまだ麻酔を使わない分娩の方が多いと聞きますが、幸いにして実家からそう遠くない東京衛生アドベンチスト病院は無痛分娩に強いと知って、即決しました。
痛いか痛くないか選べるなら痛くない方が良いから
これをワガママと言う人もいるのかもしれませんが、「痛いか痛くないか選択肢があるなら、痛くない方が良い」というのが、私が無痛分娩を知った際に即決した理由です。
中には「おなかを痛めて生むことで母性がでる」なんてことを言うクラシカルな方もいるそうですが、妊婦生活の中ですでに大変な経験は色々しているもの。あえて、出産の瞬間まで歯を食いしばる必要はないんじゃないかなと感じます。
これは無痛分娩を友達に勧める時にもよく使う例えですが…
(虫歯で歯医者さんに行った場合)麻酔無しで歯を抜くのと、麻酔有りで歯を抜くのどっちがいいですか?麻酔無しの方が痛みを感じられて、明日からの歯磨きを真剣にしようと気合が入るからおすすめです。
確かに麻酔無しの抜歯体験をしたら、死んでも虫歯にはならないぞという覚悟はできるかもしれないけれど、まぁでもいやでしょという話。これと一緒で、麻酔という選択肢があるなら、ぜひお願いしたいとシンプルに思ったので、無痛分娩を選びました。
せっかくの出産体験をトラウマにしたくないから
私も夫も3人兄弟という環境で育ったため、心のどこかで「出産は1度きりではなく、少なくとも2回はするだろうな」と思っていました。だからこそ、1回目の出産を「怖い・痛い・辛い」イメージにしたくないと思ったのもあります。
普通分娩でも「めちゃくちゃ痛かったことは、なぜか忘れちゃうんだよね」という声を見かけたこともありますが、できるならば「出産=ポジティブなイメージ」で乗り切りたい。だからこそ、選べるならば痛くない方法を選びたいと感じました。
結果として、第一子の出産は、病院の方々にも「初めての出産なのにこんなにもスムーズだなんて!」と言われるほど、とてもスルッと出てきてくれて、ネガティブイメージは一切ない体験となりました。
欧米系の友達の中では当たり前の方法だから
日本において無痛分娩がまだまだ限定的な理由として「周りの人に経験者がいない」というのもあるのかなと。すでに歴史のある方法だとはいえ、あまり耳にすることがないからこそ、ちょっと手が出しにくいのかな。
でも日本の外に目を向けると、欧米諸国では無痛分娩が当たり前の国も多いです。実際、実家の母が私を生んだ30年前でさえ、アメリカでは無痛分娩が当たり前だったそうです。
日本にいると「特別な人が選ぶ方法でしょ」というイメージがあるかもしれない無痛分娩ですが、欧米では「麻酔無しで産む人なんているの?」というくらいメジャーな方法。そう考えると、別に痛みを避けるのは逃げでもないし、文明の利器を頼っていいよなと感じます。
東京衛生病院で無痛分娩出産した時の流れ

3年前のことですが、無痛分娩で第一子を出産した時のことを振り返ってみたいと思います。あくまでも一個人の例ですが、無痛分娩でスルッと生み出した例としてご参考まで。
朝:おしるし有り
午前:じんわりと陣痛ぽい痛み
昼:ラストかもしれない!と夫とピザ屋さんへランチへ
14時半頃:陣痛を感じつつスローペースで帰宅
15時頃:陣痛のペースが定まってきて病院に連絡 ※1
16時頃:病院に到着→手続きやら状態のチェック
17時半頃:ある程度陣痛の痛みに耐えた後に麻酔開始 ※2
20時頃:ナースたちがドタバタとし始める ※3
20時半:分娩台に向かいツルっと出産
初めての出産とは思えない!と言われたほど、お手本通りというか、おしるしに始まって、その日のうちに生まれてくるというスーパー安産でした。
(※1)病院に行くタイミングは注意が必要!

午後に陣痛の感覚が狭くなってきて、手順通りに病院に電話をした時には「初めての出産だから病院に来るのは早すぎるかもしれないけど、ベッドが空いてるから不安だったら来ちゃってもいいですよ」と言われました。
でも、結果として「あの時病院に来てなければ、麻酔が間に合わなかったかも!」と言われて、早めに行動して良かったです。
出産間際に差し迫ってしまうと、麻酔が効かずに出産に挑むことになるリスクもあるそうなので、病院へ行くタイミングには注意が必要です。とはいえ、早すぎると待ちぼうけの期間が延びてしまうし、難しいところですが。
(※2)麻酔そのものは全然痛くなかった!
無痛分娩とは言え、お産を進めるためにある程度陣痛を耐えてもいいかなと思っていたので、バースプランにはそう書いておきました。よって、各種チェックをしてもらっている間は、小一時間ほど陣痛を体験してみました。
結構痛いな…と思った頃に、ようやく麻酔投入。背中に注射をされたみたいですが、感じていた陣痛と比べるとチクッと針が来るだけなのでたいしたこともなく、麻酔液が入ってくるのも不快でもなかったと記憶しています。
出産レポートなどを見ていると、麻酔そのものが痛いという説もあって、どうかな?と思いましたが、私自身はこれといって嫌なイメージも残りませんでした。ちょっとだけ陣痛を体験したのが良かったのかも!
(※3)無痛すぎてクライマックスが分からないほど

麻酔を使っていなければ「どんどん陣痛の感覚が狭まってくる!陣痛の痛みが増してくる!」と、出産に向けたダイナミックな陣痛を体感できます。だからこそ、そろそろ生まれるのでは?と妊婦さんの方も分かるものだと思います。
でも、無痛分娩を選ぶと、麻酔をしているので、これといった痛みはありません。なんとなく胎動のような感じでおなかの中がぎゅーっとしてるのは分かる程度。
だからこそ、突然ナースの方々がベッドサイドにやってきてドタバタとし始め「そろそろ分娩室ですね」「そろそろ出しましょうか」と言われて、こちらは「え?もう!?」と驚くのみ。それくらい、無痛分娩は痛くありませんでした。
第一子を無痛分娩で出産した時の思い出

無痛分娩ということもあり、陣痛を待つ部屋でも、分娩台に上がってからも、これといった痛みを感じることなく、付き添ってくれた夫・周りのナースの方々と普通にしゃべっていたなぁという印象が残っています。
痛いからと取り乱すこともなく、いきみの練習ではやたらと褒められ、実際の出産時には「ニュルッと体から塊が出てくる感」を味わうこともでき、ポジティブな記憶しか残っていません。
縫合中も痛くないから助かる
よく出産レポートなどで「生み出すことよりも、その後の会陰切開の縫合が激痛」と聞きますが、その痛みも一切ありません。
それどころか、チクチクと縫ってくれる先生と普通に会話をしていました。「ルワンダからなんですねー。珍しいですよねー」なんて雑談を、生み出した直後に、お股を縫われながらするとは!
ただし、麻酔が効いているのはあくまでも「出産の前後のみ」。この点はお忘れなきよう!
麻酔が効いたまま眠りについた夜でしたが、明け方からお股がずきずき。縫った後の痛みなのか、激しく生み出してしまった痔のせいなのか、とにかく出産明けの痛みは激しかったです。
一週間ほど「円座クッション」に座ってもどうにもこうにも痛い…という生活を強いられました。
第二子の出産も無痛分娩を選びたい

1回目の出産があまりにも快適だったこともあり、周りの友達にも「無痛分娩良かったよ!」とあちこちでおすすめしていた私。
嬉しいことに第二子を授かったのですが「間違いなく、また東京衛生アドベンチスト病院で無痛分娩!」と即決しました。単純に病院での流れを理解しているということもありますが、一度無痛分娩を経験してしまうと、これから麻酔無しで産もうとは思えないものです。
現時点で妊娠9か月に突入していて、生まれるまであと1か月というところまで迫ってきています。スムーズに無痛分娩が出来ることを願いながら、毎日を健康に過ごすよう意識しています。
まとめ:出産が怖ければ無痛分娩はとってもおすすめ

「無痛分娩」という言葉は知っているけれど、選択肢として考えたことがなかった!という友達に出会ったこともあり、私は積極的に無痛分娩の話をするようにしています。
痛いか痛くないかを選べるのであれば、そりゃ痛くない方が良いよねというのが持論です。
加えて、出産というものへの恐怖心も取り除けるし、何よりも安心して出産に挑めるなと感じています。
もしも「無痛分娩が気になるな」と感じている方で、周りの声が気になったり、よく分からないから…とブレーキをかけそうになっている方の背中を押せればと思って、記事にしてみました。
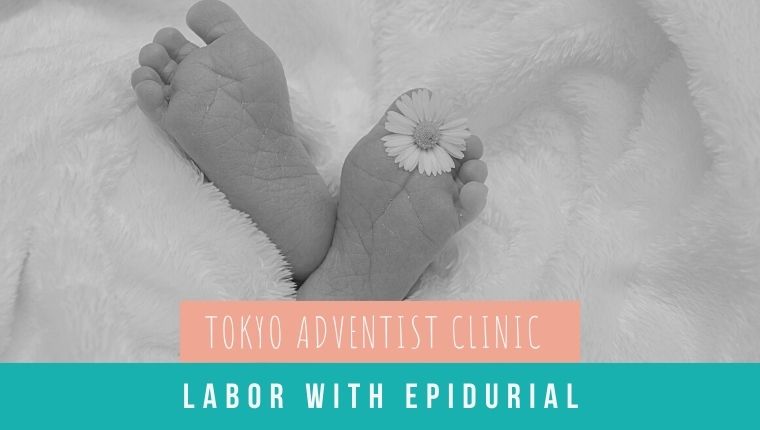










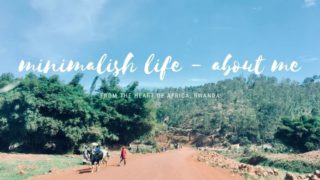
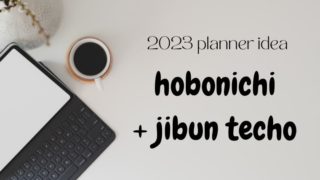
さらに何の痛みもなくツルっと出てきたので「え、もう生んだの?」とあまり実感もありませんでした。