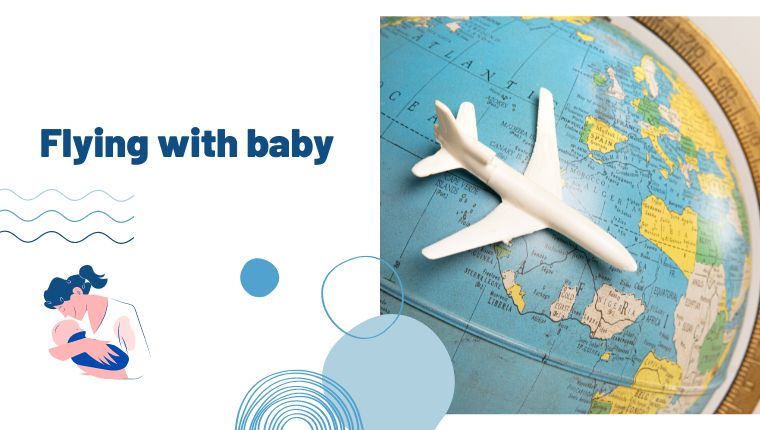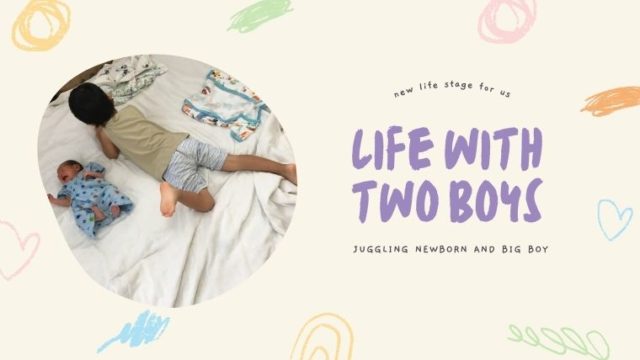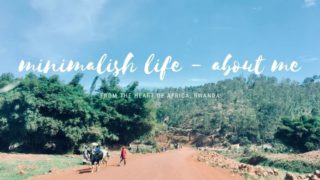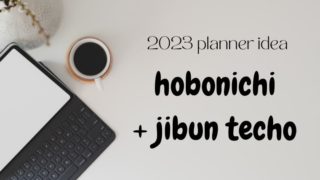こんにちは。「minimalish life」をご覧頂き、ありがとうございます。アフリカ大陸のほぼ真ん中に位置する、ルワンダよりお届けしています。
2022年夏に日本に長めの一時帰国した理由は、次男の出産!無事に赤ちゃんが生まれて、ちょうど生後2カ月になるタイミングで里帰り出産を切り上げて、飛行機で移動してきました。
里帰り出産に伴い、飛行機を使う場合は、気になる手続きが多いもの。実際に2回飛行機を使った里帰り出産をした経験を生かして、気になる点を洗い出します。
・飛行機の距離への里帰り出産を検討中の方
・赤ちゃんの初飛行機デビューを控えている方
・赤ちゃんと一緒の旅行を検討中の方
里帰り出産の前の飛行機関連のあれこれ
里帰り出産をするぞとなったら、事前にどのような手続きをしないといけないのでしょうか。
飛行機っていつまで乗って大丈夫なの?

里帰り出産というと、日本国内だと「出産の1か月前くらいに移動」というイメージがあります。ただし、飛行機を伴う移動の場合は、タイムリミットに注意が必要です。
国際線の場合:出産予定日の2カ月前まで
国内船の場合:出産予定日の1か月前まで
あくまでも一般的な数字なので、渡航予定の航空会社のウェブサイトでしっかりチェックしてください。
このリミット時期を逃してしまうと、医師の渡航許可証が必要になったり、本当にギリギリだと医師と共に移動する必要があったり…あまり直前だと、同じ姿勢で座っているのも大変ですし。
飛行機チケットの予約方法とは?
里帰り出産をする場合、往復チケットを買うことになりますが、「行きは大人だけ。帰りは赤ちゃんが増える」というケースはどうやって対応したらいいのでしょう。
実際に経験した方法としては、まずは大人の分を予約するだけで大丈夫です。無事出産が終わって、ベビーが生まれてから、帰りのチケットに赤ちゃんを追加することになります。(下にて詳しく紹介しています)
里帰りフライトに乗るときのポイントは?

おなかが大きくなってからのフライトで、私が個人的に意識したことをご紹介します。
念のため医師の渡航許可証を持ち歩く
本来であれば予定日間近になっていないと必要ではない「医師の渡航許可証」ですが、私は念のためサインしてもらい持ち歩きました。
実際チェックインのタイミングから、膨らんだおなかをみて「許可証は?」と聞かれ、乗り込むタイミングでも聞かれました。通行証代わりに持っていると安心です。
かかりつけのお医者さんに言えばすぐにサインしてくれるので、準備するに越したことありません。チェックイン時+フライト毎に提出を求められる可能性があるので、複数携帯するのが安全です。
むくみ対策でマイボトルを持ち歩く
妊娠後期はいつもよりもむくみが気になる時期。飛行機に乗ってから、ミールサービスまでドリンクが出てこないとなると、体に負荷がかかってしまいます。
私は常に水筒を持ち歩くようにしていました。乗る前の手荷物検査ではカラにさせられるけど、飛行機に乗り込むや否や(みんなが乗り込んでいる時がねらい目)、キャビンアテンダントさんにお願いしてボトルに水を入れてもらいました。
「喉かわいたんだけど、ドリンクまだかな…」とそわそわする手間も省けて、もはや妊婦でなくても、水筒はフライトのお供です。
いつもより少しだけストレッチ頑張る
医師の渡航許可証をもらった際に、お医者さんからは血のめぐりを良くするために、機内では動き回るようにとアドバイスをもらいました。
積極的に水を飲んでトイレに行ったり、なんとなくストレッチをしたり。いつもやっていることではありますが、いつもよりプラスアルファで出来るように意識しました。
出産してからの飛行機関連のあれこれ
赤ちゃんが生まれてきてからは、里帰りの引き上げに向けてどのような準備を進めていけばいいのでしょうか。
赤ちゃんのパスポートってどうしたらいいの?

国外への移動を伴う場合は、何はともあれパスポートの申請を進める必要があります。赤ちゃんが生まれて、名前が決まれば、すぐに手続きが可能です。
唯一の難関は、赤ちゃんのパスポート写真を撮ること。時代は変わり、スピードフォトでなくて大丈夫になったのだけが救いですが、決して簡単ではありません。
白いシーツを敷いた上に赤ちゃんを寝かせて、何とか前を向いていて、目が空いている写真を撮る。
我が家の長男・次男はどちらも生後2週間頃のふにゃふにゃの顔のパスポートが仕上がりました。もはや完全に別人です。
赤ちゃんのビザってどうしたらいいの?
赤ちゃんを連れていく国によっては、入国時にビザが必要な場合もあります。こればかりは国によってルールが異なるので事前にチェックをする必要があります。
・出生証明書 Birth Certificate
・戸籍謄本 Family Certificate
これらは英語にして持っていた方が安全です
事前にビザを取る必要がある国の場合、パスポート取得→ビザ申請と時間がかかるので、手続きは急いだほうが良さそうです。
赤ちゃんの飛行機チケットってどうしたらいいの?

里帰りした時は大人の分のチケットしか買っていないので、赤ちゃんのチケットはどうなるの?と心配になりますよね。
- まずは大人の分だけ予約を取る
- 生まれてから、航空会社に電話を入れる
- 電話越しに赤ちゃんの分の予約を追加
- メールにてE-チケット受領
航空会社に電話を入れるタイミングは、国内線であれば「赤ちゃんの名前が決まれば」予約が可能です。
一方、国際線の場合はパスポートナンバーを求められるケースがあります。よって、パスポート申請が終わってからの予約になります。
赤ちゃんの座席はどうなるの?

そもそも赤ちゃんは座席があるの?という疑問ですが、これは予約方法によって異なります。
あえてお金を払って座席を予約する場合
大人と同じように1席分予約すれば、機内ではゆとりをもって過ごすことができます。また席を予約することで、預け荷物の量も大人と同じ量になるので、荷物が多い時は検討すると良いでしょう。
ただし、席を予約する場合は当たり前ですがお金がかかります。子どもでも「大人の8割」くらいの費用がかかることが多いです。
座席なしでお膝で抱っこで予約をする場合(2歳未満)
2歳未満であれば、座席を予約しなくてもOKというルールの航空会社が多いです。
この場合は、大人が座席に座りながら、赤ちゃんを膝に乗せて移動となります。国際線の場合、入国税などの最低限の支払いが必要になります。
またお願いをすれば「バシネット」と呼ばれる、赤ちゃんが横になれる簡易ベッドもあります。一部の席にしか取り付けができないので、赤ちゃんのフライトチケットを予約する際にしっかりと伝える必要があります。
いざ幼児と一緒に飛行機に乗るときのあれこれ
赤ちゃんと一緒に飛行機に乗るというのはドキドキするもの。でも、個人的な経験から最低限の必要荷物だけをご紹介します。
赤ちゃんのベビーカーはいつ預けるの?

赤ちゃんとの移動で基本的について回るのがベビーカー。これはいつ預けるのでしょうか。
・カウンターでスーツケースを預ける時に一緒に
・飛行場で使って飛行機に乗る直前の扉にて
チェックインしてから飛行場の中で過ごす時間が長い場合は、ベビーカーは「扉預かり」にすると施設内でも使えるので安心です。
赤ちゃんの機内でのミルク事情はどんな感じ?

「液体の機内持ち込みが厳しいけれど、ミルクはどうしたらいいの?」と心配になるものです。実際にやってみたところ、赤ちゃんに対してはとても優しいなという印象です。
・子供用の飲み水/お湯は水筒に入れて持ち運びOK
・機内でもいつでも水筒にお湯がもらえる
・お願いすれば哺乳瓶も洗ってもらえる
子供用と言えば、セキュリティチェックの際に水筒に液体が入っていても大丈夫なケースが多いです。ミルク用のお湯だと説明すれば回収されてしまうリスクは少ないと感じました。
もしカラにするようにと言われてしまっても、飛行機に乗るや否や、フライトアテンダントさんにお願いすれば、お湯を水筒に入れてもらえます。常に手元においておきたい場合は、保温できるタイプの水筒を持参しましょう。
忘れたくない手荷物とは?

赤ちゃんとの飛行機というとあれこれ気になって、荷物が多くなってしまいがち。でも、乗り換え時の持ち運びや、機内での取り出しを考えると、荷物が大きすぎるのも考え物です。
・多めのおむつ
・多めのティッシュ
・多めのミルク
・着がえ2セットほど
・水筒(お湯用)
経験上もっていったおもちゃなどは登場しないことが多いので、必要最低限でいいかなと。長距離フライトになればなるほど、吐き戻しやよだれなどで服が汚れる確率が上がるので、着がえは多めがベターです。
万が一の一泊リスクを忘れずに
トランジットが上手くいかなかった場合など、最悪のケースに備える必要もあります。
最悪の最悪は、スーツケースは空港に預けたまま、「手荷物だけで空港ホテルで一泊」という可能性があります。
大人だけなら着がえなくても&その場で支給される食事でなんとかなりますが、子どもと一緒だとそうもいきません。特におむつ+ミルクはかさばるけれど、多めに持ち歩くに越したことはありません。
まとめ:飛行機で里帰り出産も事前準備で怖くない!

飛行機の移動を伴う里帰り出産を2回経験しました。幸いどちらのケースもトランジットでのドタバタなどはなく、予定通りスムーズに移動することができました。
フライトの前の手続きは、知っていればどれもとても簡単。やはり心配となるのは赤ちゃんとのフライトそのもの。「飛行機の中での赤ちゃんのお着換え」は毎回発生するものですし、スムーズに授乳が出来るかななどと乗るまで気になることは多いです。
でもやってみてわかったのは、荷物はピンポイントに絞って少ない方が良い。赤ちゃんを抱っこしながらの移動では、大きな荷物は持ち歩けません。だからこそ、事前の準備をしっかりとして、コンパクトに荷物を作り上げましょう。